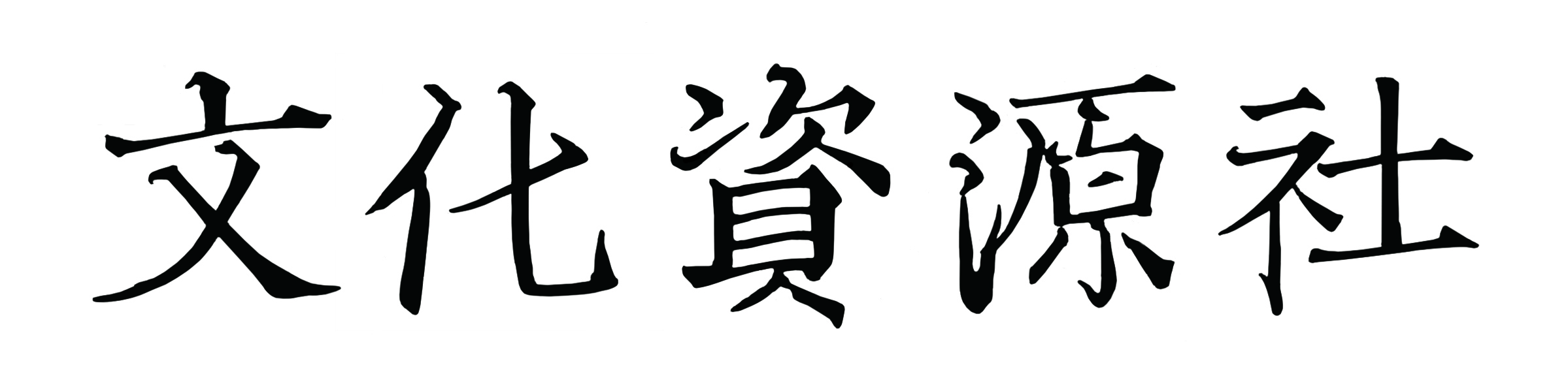近代日本美術の調査研究に朗報――『読売新聞 よみうり抄』新刊
中島 理壽
待望の書というより喉から手が出るほど欲しい書物が、戦前日本美術の調査・研究にとって即戦力となる編纂書が、この2月に刊行された。文化資源社(滝口富夫氏)から出版されたよみうり抄研究会編『読売新聞 よみうり抄 大正篇』第1巻である。
直ぐにページをめくり、(いま私が年譜の追補に取り組んでいる)藤島武二という文字を追った。すると、1912(明治45・大正元)年の1年間だけであるが、5か所にその美術家の文字が記されていた。
▲藤島武二氏 は赤坂の某富豪の依頼を受けて目下海岸を画題にしたる食堂の壁画を揮毫中なりと〔1月27日(土)〕
▲藤島武二氏 甲州山中湖附近へ写生旅行に赴きたる由〔7月25日(木)〕
▲藤島武二氏 駿州富士裾野なる某氏の別荘に在り〔8月6日(火)〕
▲藤島武二氏 甲州山中湖より数日前帰京〔8月15日(木)〕
▲藤島武二氏 赤星家の洋館応接間の壁画を依嘱せられ昨今下図製作中なりと〔8月21日(水)〕
というものである。どの記述もシンプルで、年譜作成にとってはうってつけの内容となっている。日付は本来それぞれの記事の前に置かれているが、便宜上末尾に付した。
私がかつて編纂した「藤島武二年譜」(『藤島武二画集』日動出版部 1998年9月 所収)の1912(明治45・大正元)年は大部分が展覧会出品記録や美術研究所設立といった公的な記録であるが、一つだけ、
夏 山梨県山中湖長池を旅行する。
という記述がある。早速にこの「よみうり抄」の記事を反映させて、
7月 山梨県山中湖畔の長池へ写生旅行し、8月帰京する。この間、富士山の裾野に赴く。
とし、記述にふくらみを持たせることができた。山中湖北岸の長池からは富士山の全景が眺められるという。
そして何よりの収穫は、これまでどの藤島年譜も触れることの無かった東京赤坂・赤星家の食堂や応接間の壁画を手がけた、という事実である。藤島作品の収集でも知られる富豪赤星鉄馬との関係、この年の6月に完成したというコンドル設計の赤星邸の邸内、鉄馬のいとこと結婚した藤島の妹ツルのこと等々、(私が識らないだけなのかも知れないが)興味深い世界が広がり迫ってくる。ただこの追究を続けると、この「よみうり抄」の紹介からはどんどん外れてしまうので、この辺にしよう、この「よみうり抄」には未知なる鉱脈が眠っている可能性が潜んでいるに違いない、というひと言を添えて――。
『読売新聞』の文芸面に収められたというか片隅に置かれた「よみうり抄」は、いわゆる新聞・雑誌における彙報欄というものである。文化的出来事の報道、芸術分野の論評・論説、コラムなどの寄稿文といった文章を主体とした新聞の文芸面の下、その連載小説の真上に置かれた囲み記事がそれで、藤島武二の具体例に見たような、雑報や消息を淡々と列記したものを彙報欄という。社会面の訃報欄(死亡記事)もこの類いに近い。新聞だけでなく美術雑誌にも、多くは巻末に、それぞれの雑誌によって呼称は異なるが、時報欄・展覧会案内欄・雑報欄・消息欄などがあって、これらの総称が彙報欄なのである。
この「よみうり抄」を通覧していくと、美術家の動向や美術展の開催などが次々と記載されていて、文芸面(文芸欄)と言うと近代文学の世界と思われがちであるが、何と三分の一は、大正期の美術の世界のことがらで占められている。
美術展ひとつ集中的に見ても、竹之台陳列館や表慶館、日本美術協会列品館などでの比較的規模の大きい展観もそうだが、大正期に少しずつ広がりを見せていた〈ギャラリー〉での個人展も散見され、大小様々な美術展が繰り広げられていたことが知れて興味が尽きない。画廊という呼称はこの時代はまだ使用されておらず、日比谷美術館や虎之門美術館のように「美術館」という呼称がギャラリーの意味で用いられていた。一方、画廊の嚆矢と言われている琅玕洞をはじめ、三越呉服店、本社(読売新聞社)楼上、赤坂三会堂、ヴヰナス倶楽部、三笠などの馴染深い展示空間の名前も躍る。
また、文芸誌など様々な分野の多彩な雑誌の中に混じって美術雑誌――『美術画報』(明治32年創刊)、『美術新報』(35年創刊)、『みづゑ』(38年創刊)、『書画骨董雑誌』(39年創刊)、『現代の洋画』(45年創刊)、『絵画清談』(大正2年創刊)などの主要目次である「雑誌要目」が見られるのも参考になりとてもありがたい。特に新年号の「雑誌要目」は壮観そのものである。
図書館関係の記事が多いのも意外であった。
▲日本美術協会 では其所蔵図書の整理が旧臘完結したので本月十七日から図書室を開始し、会員並に会員の紹介者に限り閲覧を許す、〔大正3年1月16日(金)〕
という記事が見つかった。日本における美術図書室の最初なのであろうか。その後の記事に、事務室のひと間を充てたので20名以上の閲覧は制限する、とあるのもほほえましい。蔵書数は約500部とあるから本格的な図書室の誕生と言える。
休み休みページをめくっていると、ふと次のような文字が目に飛び込んできた。
▲長沼智恵子女史 は郷里福島に帰省中なりと〔大正元年8月18日(日)〕
そして、故北川太一さんの顔が浮かんだ。この2行にどんな意味が隠されているのか私には見当がつかないが、「そうだ、この『読売新聞 よみうり抄』の発刊を一番喜ばれているのは北川さんにちがいない」と思った。北川さんは高村光太郎研究の第一人者で、それゆえ「長沼智恵子」から北川さんを連想したことは間違いないが、それだけではなかった。北川さんは、誰よりもこの「彙報欄」の必要性を熟知していたよき理解者だったからである。
先年、『美術新報』のDVD版が実現した際に「DVD版『美術新報』に驚く」という一文を寄せてくださり、彙報欄の大切さを説き、それが検索できる確かさ充実ぶりを実感されていた。北川さんは、5年前の2020年1月12日に亡くなられたという。もちろん無いものねだりだが、この『読売新聞 よみうり抄』をぜひ見ていただきたかった。
『読売新聞』の文芸担当の記者たちが情報をこまめに足で集め記事にしてきた「よみうり抄」、その結実が、その凄さが、110余年の歳月を経て、今こうして、現代の美術研究者や美術関係者の前に繰り広げられているのだ。大事に使って行かなければ、と思う。
(なかじま・まさとし 美術ドキュメンタリスト)