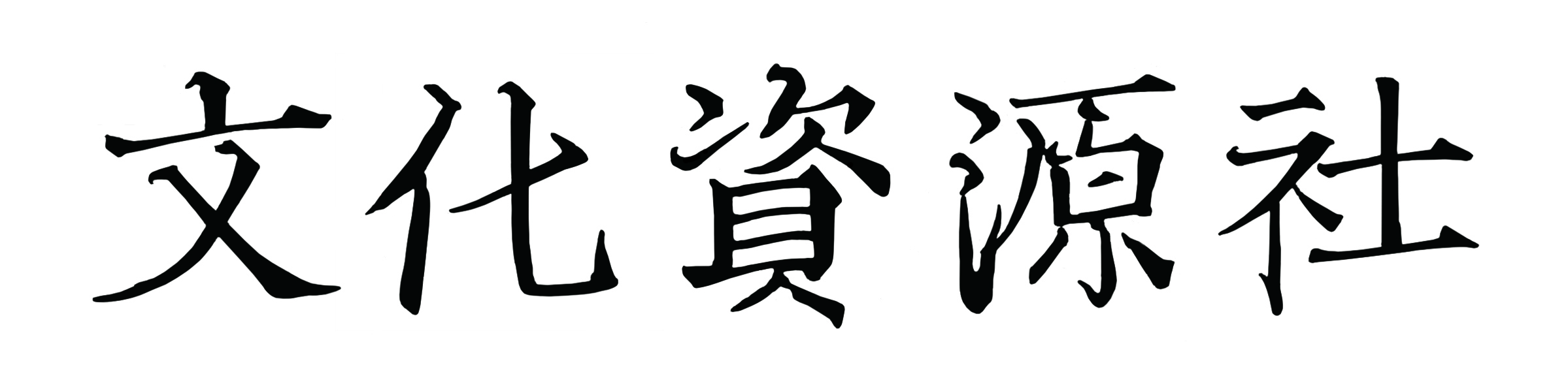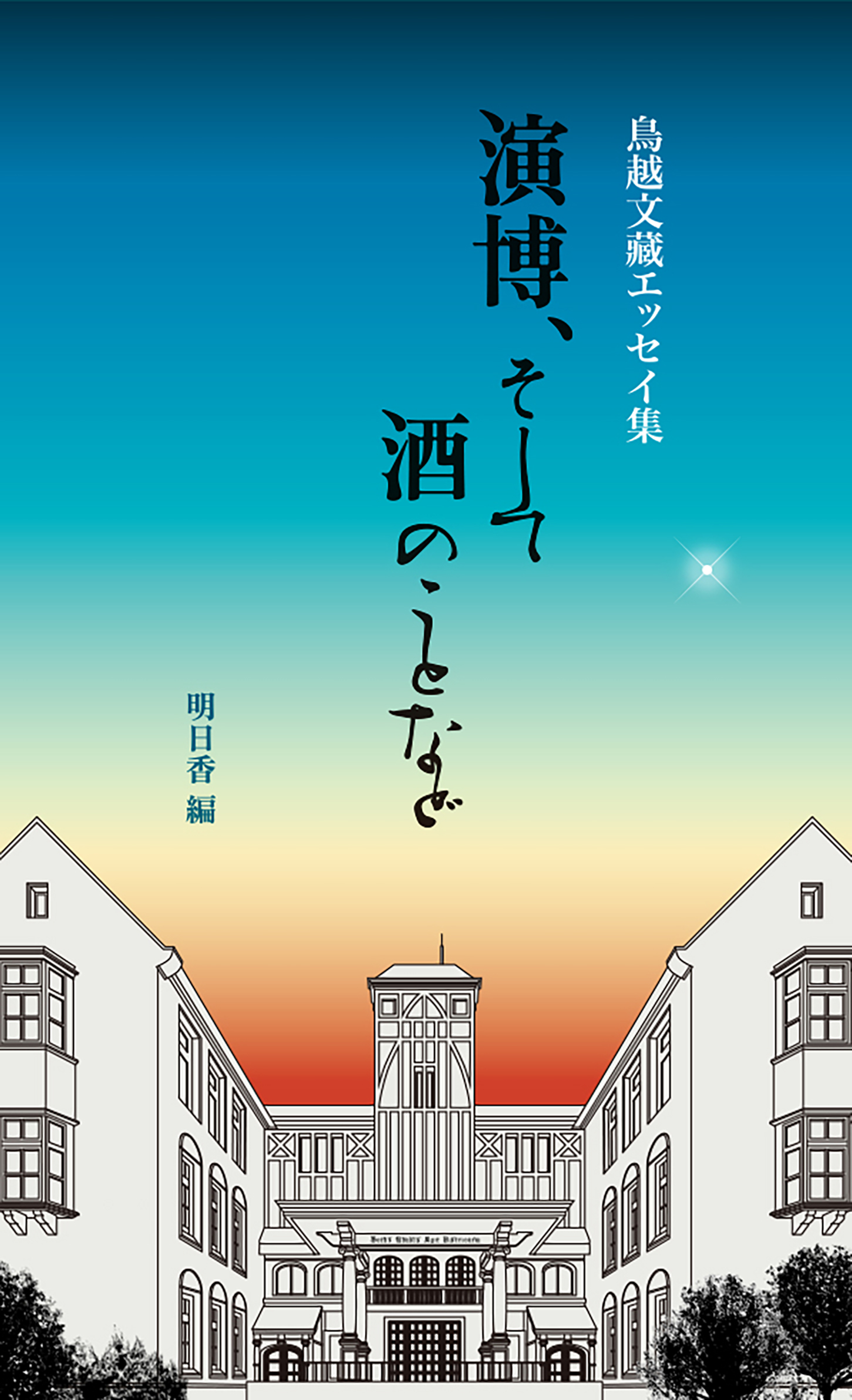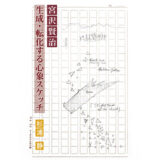| タイトル | 演博、そして酒のことなど 鳥越文藏エッセイ集 |
| 著者 | 鳥越文藏(著/文)、明日香 (編) |
| 判型/頁 | 新書版 248ページ |
| 定価 | 1,500円+税 |
| ISBN | 978-4-910714-02-8 |
| Cコード | C0295 |
| 発売日 | 2022年9月18日 |
「俺ほど世界で一番演博を愛している者はいない」といつも仰っていた鳥越文藏先生のエッセイ集。
昭和3年に坪内逍遙によって創設された演劇博物館にイノベーションを起こした中興の祖である著者は、それまで学内に向かって開かれていた演博の方向を外部に向け、だれでもが利用できる開かれた演博にしたいという強い思いをもっていた。そして、時代の潮流と、腕っこきの弟子達と協力を得て、デジタル化の先鞭をつけ、「早稲田の演博」を「世界のenpaku」と呼ばれるまでに変えた。今から20年ほど前に書かれた文章は、博物館・資料館・文学館などの学芸員ばかりではなく、古い組織の体質を仲間を信じて共に改革していこうとする全ての人の共感をえられるでしょう。
そして、大学退任の後に書かれた酒と美味いものをはじめとする悠々自適の文章、そして、老いについても少々。
あとがきにかえて
父鳥越文藏は2021年4月5日に亡くなりました。あいにくのコロナ禍のため、身近にいるごく少数の方々のみで、密葬の形で葬儀を行わざるを得ませんでした。
2022年9月18日、コロナ禍は未だ収束しておりませんが、父の大好きだった早稲田、そして演劇博物館の主催で、大隈講堂にて父のお別れの会を開催して頂く運びとなり、感謝の気持ちでいっぱいです。
本書は、「なにか記念になる刷り物を、来て頂いた方に配ったら」という、7月のお別れの会の相談の席上での話から始まりました。立命館大学の赤間亮先生が、父がかねてより書斎の一角に纏めて置いた自分の書いたものとアルバムを、画像データベースの形に整理して下さいました。それをベースに、文化資源社の滝口富夫氏が編集・製作の音頭をとってくださいました。
本書には、一つは、父の大好きだった演博を館長としてどのように運営していったのか、もう一つは、演博に負けないほど好きだったお酒にまつわる話などを集めました。これは主として、東海志にせの会が発行していた『あじくりげ』という雑誌に寄稿したものです。多くの方がご存じない晩年の父の素顔が表れているように感じます。
皆さんの書棚の片隅に収めて頂き、ときどきお酒のお供にしていただければ幸いです。
なお本書の製作にあたり、原稿を快くご提供くださった演劇博物館、神戸女子大学古典芸能センター、八木書店、親切にアドバイスをくださった日本俳優協会の浅原恒男相談役とコテンゴテンの峯田悦子社長、短時間で素敵なレイアウト・デザインをしてくださったデザイナーの南知子氏に深く感謝致します。
2022年8月28日
鳥越明日香
この本を、私どもから出版させていただける、そういったご配慮をいただけまして、大変光栄に思い、御遺族および関連各位に対して深甚の感謝を捧げます。
有り難うございました。
先生とは演博を始め、各所で度々仕事の打合をしました。大体、午後のちょっと遅め。
そして「今日は、真っ直ぐ社に戻らなきゃならないのか?」
という先生の一言は、あらかじめ織込み済み。
そんな思いは私だけではないようで、
表紙のデザインは、そんな状況を俳優協会相談役の浅原氏主導のもと、まとめていただきました。
先生と接した多くの方には共通する思い出があると思います。
大部恥ずかしいけど、本書は間違いなく「僕の好きな先生」であるわけで、
きっと先生と接した多くの人もそうだろうと思います。
だから多くの人に手に取って読んで欲しいと思います。
版元の親爺謹白
鳥越文藏(著/文)
故人。早稲田大学名誉教授・早稲田大学坪内博士記念演劇博物館館長(第五代)。日本近世演劇研究者。
明日香(編集)
鳥越文藏長女
演博
私の演博的自叙伝
近時申報
酒のことなど
ショウチュウ
ビール
ワイン
サケ
勿体ないも卑しいから
味痴 未知 道
珍しきが花なり
無知不実行
毒試
思考の内外
何はともあれ旨いもの
民主主義万歳
食通にはなれず美食家にはならず
飲食に関わる音
海国萬歳
私の厨房歴
老いの楽しみ
貧しい食生活
写真機
魚のこと
ことば
好き嫌い
一周忌の酒
病気上手の死に上手
祐田善雄先生と「義太夫年表」
郡司先生追悼
夢多き友を悼む(追悼信多純一氏)
追悼文(ドナルド・キーン氏)
鳥越文藏略歴(カラー口絵16頁)
附り
近代博多興行史 目次
はじめに
研究篇
第一部 総論 地方興行史概説
第一章 劇場と興行
第一節 武田家と興行
武田政子氏との出会い 武田一族 与吉の芝居道楽
第二節 劇場通史
劇場一覧 博多劇場史の展望
第三節 興行を支える諸制度
請元 請元としての武田与吉 劇場経営者と劇場
第二章 巡業の実態
第一節 初日から千秋楽
町廻り(顔見世) 式三番引き抜きだんまり 替り狂言から千秋楽 番付
第二節 衣裳・小道具・大道具 衣裳・小道具 大道具 劇場ごとの規格
第三節 交通機関の発達と巡業
鉄道敷設前 明治二一年の事例 巡業ルート
第二部 博多興行通史
第一章 伝説の劇場
第一節 宝玉舎をめぐって 宝玉舎 柳町大芝居と永楽社 集玉社
第二節 西門橋教楽社と市川右団次 西門橋教楽社の存在 市川右団次 明治一〇年、一一年の右団次
第三節 鳥熊芝居および集観舎
鳥熊伝説 集観舎のお琴新兵衛
第二章 「社」の時代
第一節 教楽社開場
小田部博美と井上精三の回想から 中村駒之助
第二節 劇場に電灯ともる
大阪中座 尾上多賀之丞 対抗する永楽社
第三節 中村鴈治郎
第三章 日清戦争前後
第一節 我童・福助招聘合戦
明治二五年の状況 我童の招聘ならず 時助・右左次一座から左升一座
第二節 新演劇の興隆
日清戦争劇ブーム 博多の新演劇 際物としての新演劇
第三節 教楽社・永楽社の危機
内紛 教楽社売買問題 東京俳優の招聘計画
第四章 混乱・低迷
第一節 北九州・筑豊の活況
若松旭座開場 小倉旭座・小倉常盤座・直方日若座 博多の地盤沈下 運動場
第二節 博多の大劇場計画
「博多演劇会社」あるいは「福博演劇会社」 教楽・栄楽両劇場の対応
第三節 コレラ
コレラ発生 興行解禁と教楽社・栄楽座の迷走
第五章 諸芸の開花
第一節 映画伝来
自動写真・活動写真 「シネマトグラフ」と「ヴァイタスコープ」 再び教楽社 活動写真の進歩 日露戦争と活動写真 日露戦争以後
第二節 女義太夫
博多の寄席 女義太夫
第三節 浪花節
宮崎滔天と桃中軒雲右衛門 「浮かれ節」から「浪花節」へ 日露戦争と桃中軒雲右衛門
第四節 子供芝居
第六章 「座」の時代到来
第一節 明治座と寿座
開場 武田与吉の「座」の時代 教楽社退転
第二節 新しい芝居
片岡我当の「桐一葉」 実川延二郎 尾上菊五郎・市村羽左衛門・尾上梅幸
第三節 鴈治郎と巌笑、猿之助と八百蔵 嵐巌笑 中村鴈治郎二度目の来演 市川八百蔵と市川猿之助ほか
第七章 「劇場」の時代
第一節 博多座
九州大学誘致と遊廓の移転 博多電気軌道 博多座の構想 左団次・喜多村緑郎
第二節 九州劇場
栄座 九州劇場開場
第二節 松竹の全国制覇と大博劇場への道
第三部 川上音二郎
第一章 名古屋の川上音二郎
第一節 川上音二郎の出発点
なぜ名古屋か 明治一五年名古屋説をめぐって
『名古屋新聞』 『愛知新聞』の新出記事
第二節 川上音二郎と立憲政党
川上の所属 甲田良造をめぐって 立憲政党という組織
第三節 丁年問題その他
渡部虎太郎 生活者としての演説遣い
第二章 博多の川上音二郎
第一節 寄席芸人時代
前史 明治二一年教楽社・明治二二年開明舎
第二節 新演劇
明治二六年 教楽社
第三節 正劇
明治三七年 教楽社
第四節 円熟
明治四〇年 教楽社 明治四三年 博多座 明治四四年 明治座
第三章 終章にかえて
第一節 「みもの、ききもの」をめぐって
第二節 地方興行史研究の展望
新演劇の展開 ジャンルの境界線
引用文献一覧
資料篇
博多興行番付目録
博多興行年表 明治篇
初出一覧
あとがき
索引
上記内容は本書刊行時のものです。