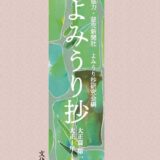| タイトル | 読売新聞 よみうり抄 大正篇 巻次:第1巻 |
| 著者 | よみうり抄研究会(編集) |
| 判型/頁 | A5判 576ページ 上製 |
| 定価 | 16,000円+税 |
| ISBN | 978-4-910714-11-0 |
| Cコード | C3073 |
| 発売日 | 2025年2月15日 |
「よみうり抄」とは読売新聞が、明治31年10月6日から毎日掲載をはじめた、芸術家(作家・画家・演劇家)や学者などあらゆる文化人の短信・消息・ゴシツプを取り上げた小欄の名称。本書は大正期の「よみうり抄」をすべて翻刻した第1巻目。
現在では、この小欄の集積が、今となっては客観的な記録・情報となり、文化人がいつどこに出かけ、誰に会い、何をしたかという膨大な情報群となっているが、従来、この欄を通覧することが難しかったものを、全5冊に翻刻。
明かな誤植を訂正した他、印刷・マイクロ化・デジタル化の都合で不読となった文字を可能な限り補記し「よみうり抄」の全文を活字化。
凡例
一、本巻は『読売新聞「よみうり抄」大正期』第一巻として、明治四十五・大正元年(一九一二)~大正三年(一九一四)の『読売新聞』に掲載された彙報欄「よみうり抄」を収録した。
一、全体の体裁は「よみうり抄」に従い、項目ごとに見出しと記事本文を掲げたが、一行の字詰めや活字の大小などをそのまま踏襲したものではない。明治四十五・大正元年の「よみうり抄」は、見出し項目を◎印で掲げているが、『読売新聞「よみうり抄」大正期』全体の体裁に揃えて▲印とした。また大正三年の「よみうり抄」には、見出し項目と本文が一続きになっているものがあるが、全体の体裁に揃えて一字あきとした。見出しの圏点や本文の振り仮名も原則として省略し、必要と思われるもののみ残した。
一、漢字の字体は、原則として新字体(常用漢字)を用いた。ただし、人名・地名・団体名・作品名などの固有名については、現在でも旧字体・異体字表記が一般的と思われる場合に限り、旧字体・異体字を残したものがある。
一、仮名遣い、送り仮名、反復記号などについては、表記の混用や清濁の有無も含めて原文通りとしたが、明らかな誤りと判断される場合には訂正した。また、句読点「。」「、」や中点「・」、括弧「 」『 』などの符号類についても、原則として原文通りとしたが、脱落や、行末で省略されていると判断したものについては、適宜補った。
一、「よみうり抄」には、彙報欄の常として、誤記・誤植の類が少なくない。このうち、人名・地名・団体名・作品名などの固有名について、明らかな誤りは訂正した。ただし、作品名・題名・書名等については、成立過程における表記の揺れや構想の変化を反映している可能性があるので、そのままにした場合がある。
一、原文に疑義がある場合には「ママ」を付してそのままとした箇所がある。また、判読が困難な箇所や脱字箇所については□としたが、前後の文脈から推測が可能なもの、あるいは他の資料などから確定できたものについては適宜補った。
一、「よみうり抄」が掲載されなかった日は、日付の下に「休載」と記し、新聞の休刊日には同じく「休刊」と記した。
一、本巻には、「よみうり抄」の名を冠していないが、紙面構成上「よみうり抄」に相当すると判断される無題の消息記事(大正二年二月六日付)や雑誌要目(大正三年十二月二十六日付)も収録した。ただし、その他の新刊案内、新刊紹介の類は対象としていない。
一、作成に当たっては、マイクロフィルム版「読売新聞」(読売新聞社、一九七四年)、及び「読売新聞」オンラインデータベース「ヨミダス」を参照し、大妻女子大学、九州大学、立教大学の学生や関係者をはじめとする多くの方々のご協力を得た。作業に従事していただいた方々、及び使用を許諾された読売新聞社に感謝申し上げます。
よみうり抄の具体的な記事は、Xに「#今日のよみうり抄」としてほぼ毎日ポストしていますので、それを見ていただくと有り難く存じます。
一つ一つの記事は、何の変哲も無い新聞の短信で、基本「誰が何をした」ですが、読む人によっては、ピンッ、と来て、情報が無限に繫がり沼る情報の集積です。
よみうり抄研究会(編集)
石川巧 立教大学教授
杉浦静 大妻女子大学名誉教授:代表
須田喜代次 大妻女子大学名誉教授
滝上裕子 明治大学他非常勤講師、立教大学日本学研究所研究員
十重田裕一 早稲田大学教授
前田恭二 武蔵野美術大学教授
宗像和重 早稲田大学名誉教
山岸郁子 日本大学教授
明治45年1月から、大正3年12月まで(担当:宗像和重)
解説
大正期・読売新聞「よみうり抄」にみる文藝彙報欄(滝上裕子)
近代博多興行史 目次
はじめに
研究篇
第一部 総論 地方興行史概説
第一章 劇場と興行
第一節 武田家と興行
武田政子氏との出会い 武田一族 与吉の芝居道楽
第二節 劇場通史
劇場一覧 博多劇場史の展望
第三節 興行を支える諸制度
請元 請元としての武田与吉 劇場経営者と劇場
第二章 巡業の実態
第一節 初日から千秋楽
町廻り(顔見世) 式三番引き抜きだんまり 替り狂言から千秋楽 番付
第二節 衣裳・小道具・大道具 衣裳・小道具 大道具 劇場ごとの規格
第三節 交通機関の発達と巡業
鉄道敷設前 明治二一年の事例 巡業ルート
第二部 博多興行通史
第一章 伝説の劇場
第一節 宝玉舎をめぐって 宝玉舎 柳町大芝居と永楽社 集玉社
第二節 西門橋教楽社と市川右団次 西門橋教楽社の存在 市川右団次 明治一〇年、一一年の右団次
第三節 鳥熊芝居および集観舎
鳥熊伝説 集観舎のお琴新兵衛
第二章 「社」の時代
第一節 教楽社開場
小田部博美と井上精三の回想から 中村駒之助
第二節 劇場に電灯ともる
大阪中座 尾上多賀之丞 対抗する永楽社
第三節 中村鴈治郎
第三章 日清戦争前後
第一節 我童・福助招聘合戦
明治二五年の状況 我童の招聘ならず 時助・右左次一座から左升一座
第二節 新演劇の興隆
日清戦争劇ブーム 博多の新演劇 際物としての新演劇
第三節 教楽社・永楽社の危機
内紛 教楽社売買問題 東京俳優の招聘計画
第四章 混乱・低迷
第一節 北九州・筑豊の活況
若松旭座開場 小倉旭座・小倉常盤座・直方日若座 博多の地盤沈下 運動場
第二節 博多の大劇場計画
「博多演劇会社」あるいは「福博演劇会社」 教楽・栄楽両劇場の対応
第三節 コレラ
コレラ発生 興行解禁と教楽社・栄楽座の迷走
第五章 諸芸の開花
第一節 映画伝来
自動写真・活動写真 「シネマトグラフ」と「ヴァイタスコープ」 再び教楽社 活動写真の進歩 日露戦争と活動写真 日露戦争以後
第二節 女義太夫
博多の寄席 女義太夫
第三節 浪花節
宮崎滔天と桃中軒雲右衛門 「浮かれ節」から「浪花節」へ 日露戦争と桃中軒雲右衛門
第四節 子供芝居
第六章 「座」の時代到来
第一節 明治座と寿座
開場 武田与吉の「座」の時代 教楽社退転
第二節 新しい芝居
片岡我当の「桐一葉」 実川延二郎 尾上菊五郎・市村羽左衛門・尾上梅幸
第三節 鴈治郎と巌笑、猿之助と八百蔵 嵐巌笑 中村鴈治郎二度目の来演 市川八百蔵と市川猿之助ほか
第七章 「劇場」の時代
第一節 博多座
九州大学誘致と遊廓の移転 博多電気軌道 博多座の構想 左団次・喜多村緑郎
第二節 九州劇場
栄座 九州劇場開場
第二節 松竹の全国制覇と大博劇場への道
第三部 川上音二郎
第一章 名古屋の川上音二郎
第一節 川上音二郎の出発点
なぜ名古屋か 明治一五年名古屋説をめぐって
『名古屋新聞』 『愛知新聞』の新出記事
第二節 川上音二郎と立憲政党
川上の所属 甲田良造をめぐって 立憲政党という組織
第三節 丁年問題その他
渡部虎太郎 生活者としての演説遣い
第二章 博多の川上音二郎
第一節 寄席芸人時代
前史 明治二一年教楽社・明治二二年開明舎
第二節 新演劇
明治二六年 教楽社
第三節 正劇
明治三七年 教楽社
第四節 円熟
明治四〇年 教楽社 明治四三年 博多座 明治四四年 明治座
第三章 終章にかえて
第一節 「みもの、ききもの」をめぐって
第二節 地方興行史研究の展望
新演劇の展開 ジャンルの境界線
引用文献一覧
資料篇
博多興行番付目録
博多興行年表 明治篇
初出一覧
あとがき
索引
上記内容は本書刊行時のものです。
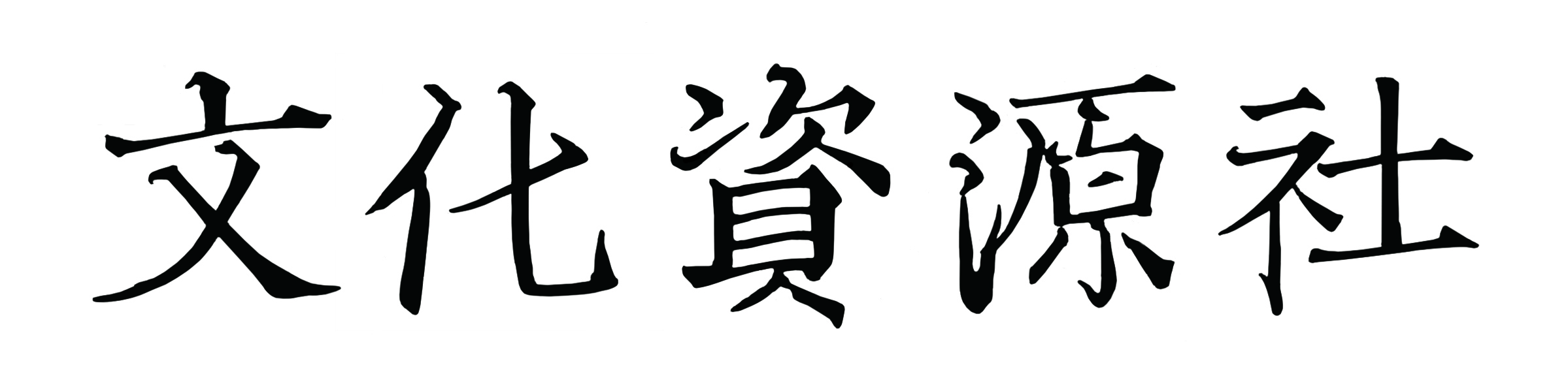
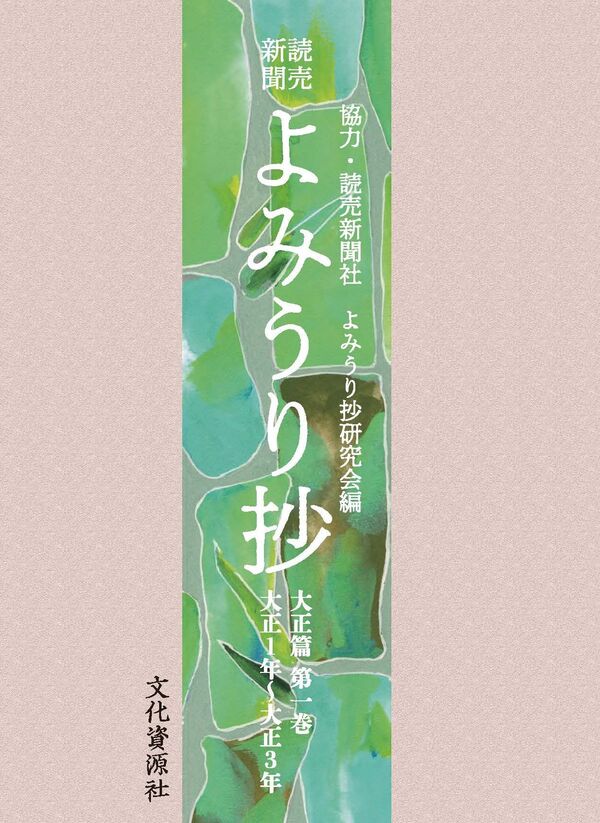
-160x160.png)